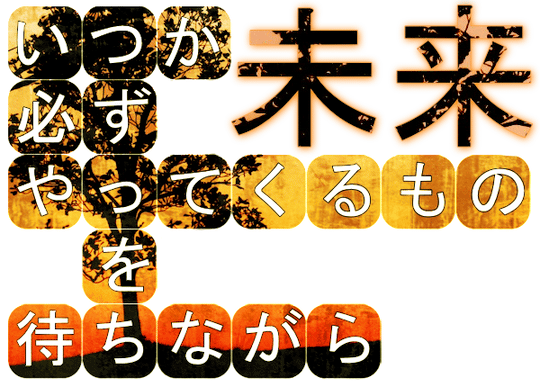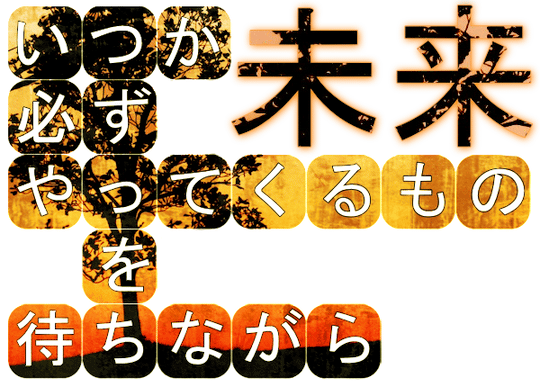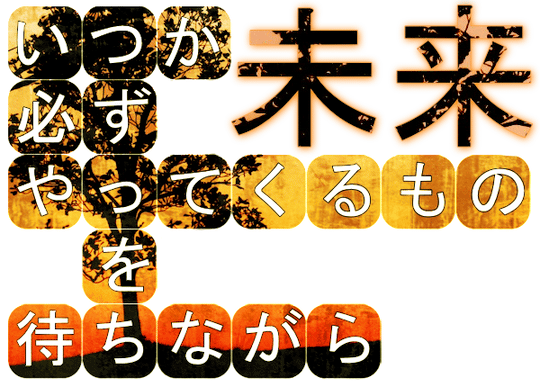
有名な道。一本の木。夕暮れ。
「やあ、かわいそうなお嬢さん」
東から来た男が言った。
白羽のついた大きな帽子が陰になり、その顔はわかりづらい。
帽子からこぼれた髪は癖のある褐色で、金のリボンでひとくくりにされていた。
錦糸で刺繍がされた派手な上着、一抱えもある見事な竪琴《リュラー》で、男の職業がわかる。
「やあ、幸せそうなおじさん」
木陰に座っていたリリーは口を開いた。
首都ダーナの西地区だけあって、この辺りは人通りが絶えない。
景色だった人たちが足を止める。あるいは行き過ぎるのを利用して二人をちらりを見やる。中にはご丁寧にもにやにやと笑いながら、ささやきを交わす者たちもいる。
男が指を鳴らす。
白い指にはめられた指輪が夕日の光を弾いて輝く。それはそれは、無駄に。盛大に無駄に。煌いた。
「おじさんはヒドイな。
これでも、お兄さんのつもりなんだよ」
大げさな身振りを交えながら、男は言った。
リリーもぎこちなく指を鳴らす。
これで会話は、閉じられた。道行く人たちには届かなくなるはずだ。
「歳はいくつ?」
「ん? ああ。僕は27歳だ」
男はワンテンポ遅れて答える。
「おじさんで十分」
27歳。立派なおじさんだ。
リリーよりも、10歳以上も上なのだから。
「名前で呼んでくれないか?
こう見えても、ジョンという立派な名前があるんだよ」
派手な外見に見合わず、非常に地味な名前だった。
どこの世界でもいるような平凡な名前に、リリーは面倒なことになったと思った。
「何か用ですか?」
声が硬くなる。
「君はずっとここにいるね」
ジョンは歩きだす。
リリーが背を預けている一本の木をゆっくりと回るように。
「僕が知っている限り、48日と23時間。
決まって夜6時に、この一本の木の下にいる。
だいたい1時間。遅くても夜8時には切り上げる」
「ストーカー? 訴えるけど」
リリーは地面を見つめる。
下手に顔を上げて、男と目が会ったらマズイ。
寒さを感じない世界だというのに、背筋が凍る気がした。
「僕は吟遊詩人《バード》さ。
そんな無粋な職業じゃない。君を付け回したりはしていない。
その証拠に、僕はここの君しか知らない。
まあ、記念すべき日に一曲」
ジョンは指を鳴らす。
「さあさあ、道を急ぐ皆さん。
ちょっとばっかり足を止めてはどうでしょう。
行き過ぎる時間は黄金。出会いは別れの始まり。
ここに居合わせたのも神様の織り上げた糸というのなら、ここで交わるのも運命。
夕暮れに相応しい恋物語をひとつ。拍手喝采は曲の終わった後に」
朗々と口上を述べた吟遊詩人《バード》は歌いだす。
首都ダーナでもお目にかかれないほどの、祝歌。
物知らずのリリーでも、それがスゴイことだとわかった。
名前を聞いた時点でヤバイとわかっていたことだけれど、本格的にヤバイ。間違いなくジョンはヘビーユーザーだ。
あるいは運営側の人間かもしれない。
仮想現実《イッグドラシル》。
理想の自分を演じられるネットゲームとして、発表されて数年。その人気は世界的なもので、《イッグドラシル》にキャラクターを持っていることが当然という風潮が生まれつつある。
リリーの通っている学校でも、メールアドレスの交換の次に、《イッグドラシル》のキャラクター名を教えあう。携帯電話《モバイル》ゲームすらしないリリーも、キャラクターだけは持っていた。
もっとも、ほとんどプレイをしていなかったから所持品は初期状態に近い。唯一の財産は、身に着けている黒いワンピースだけ。防御力はゼロに等しく、装飾性もないから、売ったところでたいした金額にはならない。街の外に落ちている石コロのほうが貴重だった。
ジョンは指を鳴らす。
声を利用したチャットが「ささやき」状態になる。プレイヤー同士の一対一の会話だ。
「ストーカーじゃないなら、出会い系?」
リリーは言った。どっちも最悪だ。
「せめてナンパと言ってくれないかな?
どころで、君の待ち人はどんな人なんだい?」
竪琴《リュラー》が鳴る。
指で爪弾いたのだろう。吟遊詩人《バード》専用のエモーションだ。
「どうして人を待っている、って思うんですか?」
「動かないからさ。
ここが約束の場所なんだろう?
約束したのがこの場所だから、君は動けない。
君の待ち人はそそっかしいね。
場所と時間は知らせたのに、日付は忘れたんだね。
こう見えても顔が広い。
知り合いの名前を教えてくれないかい?」
ジョンはぺらぺらと言う。
「ゴドー」
「それは不吉な」
「知ってんの?」
リリーは顔を上げた。
「そりゃあ、吟遊詩人《バード》だからね。
有名すぎるシナリオだ。
『有名な田舎道。一本の木。夕暮れ。』浮浪者が二人」
詠うような口調で吟遊詩人《バード》は「ゴドーを待ちながら」のと書きを言った。
「ゴドーは結局、来ないんだよね」
少女は結末を確認した。
有名な戯曲だったけれども、リリーは簡単なあらすじを知っているだけだ。……結末だけを知っているだけだった。
「それは幕の開いている時間の中だけの話さ。
もしかして、終幕の先にゴドーは来たかもしれない」
吟遊詩人《バード》は言った。
ジョンはいいボイスチェンジャーを使っているのだろう。耳に届く声は良かった。
「おじさんは幸せそうだね」
「それは大変結構なことだよ。かわいそうなお嬢さん」
「リリー。……私の名前」
「善い名前だ」
男は情感たっぷりと言う。
「適当につけたんだけど」
興味のないゲーム。面白いとは思えなかったから、適当にキャラクターを作った。名前も同じだ。
深い意味なんてなかった。
「選ばれるというのは幸運だよ。
さあ、君の待ち人の話をしようか。
僕と君の、今のところの共通項だ」
ジョンは座った。
器用にリリーの隣。キャラクター、一人分を空けて腰を下ろした。
「知ってどうすんの?」
「最愛の恋人かい? それとも堅い絆で結ばれた親友かい?
君にとって、とても大切な人なんだろうね」
ジョンは自分の話を続ける。リリーはあきれながら
「どうして、そう思うの?」
と質問し返した。
「48日間。一月半以上。
毎日、同じ時間、同じ場所で待っている。
情熱的だ」
「惰性」
「僕が話しかけるのは迷惑だろう?
しかも、さっき悪目立ちした。もう話題になっているんじゃないかな。
それでも、君はここを動かない。
十分に情熱的じゃないか」
ジョンは言った。
先ほどのパフォーマンスはわざとだった。ようだ。
この世界は仮想現実だから、舞台《器》は何も変わらない。プレイヤーの意思でしか変化しない。キャラクターは何時間でも立っていられるし、喉も渇かないし、トイレに行きたくもならない。世界は意思と行動でしか、変わらないのだ。
「それで、君は誰を待っているんだい?」
「そういうおじさんこそ」
「ナンパ中だよ」
「KYとか言われない?」
「空気は読むものじゃない。作るものだよ。
吟遊詩人《バード》だからね」
ジョンは膝に抱えた竪琴《リュラー》を爪弾く。
「暇人。狩りにでも行ったら?
ギルドは? 公式イベントは?」
「夜6時から8時まで。
ここで時間を使うのが日常なんだよ」
「仕事してないの?」
「この時間はね。
僕のリアルが気になるかい?
だとしたら、ナンパはまずまずの成功ということになるけれど」
「いつまでいんの?」
「君がこの世界を去るまで」
「ご苦労さま」
どんな言葉を吐いても、ジョンは立ち去る気はないようだった。
リリーは造り物の空を見上げる。何度目かの夕暮れは出て行こうとしていた。また夜が来て、朝が来るのだ。
「僕はこの世界を愛している」
本当に大切なことを打ち明けるときのように、ジョンは静かに言う。
「ニセモノだよ」
リリーは皮肉った。
「そこがいい。
ホンモノは間に合っているからね」
「変わってるって言われない?」
「褒め言葉だね。ありがとう」
「どこがいいの?
こんな造り物」
48日間、毎日ログインしたけれど、好きにはなれなかった。
ゴドーと同じだ。
……リリーは好きにはなれなかった。
「死の概念が希薄なところが気に入っている。
役者《キャラクター》の死はデータだけ。何度でも、道を歩ける」
「その代わりにハッピーエンドもないみたいだけど?」
「シナリオがあるほうが好きかい?
退屈な人生だ。
人の数だけドラマがあってもいい」
「役《ロール》」
RPG。ロールプレイイングゲーム。
仮想現実にいる理想の自分をロールプレイするのは、楽しくない。
どれだけ理想の外見、理想の能力を手にしても、面白くない。
本当の自分を置いてきぼりにしているから……なのかもしれない。
どうしてもわからない。
「そう、僕は吟遊詩人《バード》だ」
ジョンは肯定する。
それが愛するということのなのかも知れない。
「おじさん、幸せそうだね」
リリーは言った。
「そして、君はかわいそうだ」
ジョンは優しい声で言う。
「今日でおしまいだから」
かわいそうな……リリーは言った。
とても不幸で、とても悲しい。誰が見たってかわいそうな「自分」を認めた。
「なるほど。それじゃあ、君にプレゼントをしよう」
ジョンは指を鳴らす。トレードするためのウィンドウが開く。
「その服によく似合うよ」
ウィンドウの中には、白い百合の花。この世界では回復アイテムの材料になるものだ。
それがトレード用のウィンドウいっぱいにあった。
素材とはいえこれだけの量を持ち歩けば、他の所持品はアイテムポーチに入らないだろう。
この世界では、百合は石コロよりも貴重とされている。露店を最大限に利用しても、1時間や2時間では集まらない量があった。
「おじさんは普段は何をしている人なの?」
気おされながらリリーは訊いた。
「普段? 半年前にも、やっぱりここにいたよ。
夜6時から8時までここで時間を使うのが、日常だと言っただろう?」
「もしかして、ここで露店をしてたの?」
「百合は扱っていなかったけれどね」
ジョンは言った。
「ありがとう」
リリーはトレードを完了した。
所持品の空欄が百合で埋め尽くされた。
「君はもっと笑ったほうがいい。
魅力的だからね」
「データが?」
「声には感情が宿るものだよ。
ちょっと注意すれば画面の向こうの人物の表情が見える」
吟遊詩人《バード》らしい言い回しだったけれど、リリーにはロールプレイしているようには、もう見えなかった。
「どうして、二人はゴドーを待っていたんだろう」
リリーは尋ねた。
「ゴドーは希望だったんだよ。
いつか、必ず来ると約束された未来だった。
だから二人は待っていたんだ」
「詩人だね。
本当は、ここで待っていても来ないってわかっていたんだ」
リリーは変化した空を見た。
夕暮れは去り、夜が来ていた。
輝く一番星。
データのくせに、それは美しかった。現実みたいな顔して、そこにいる。
「でも、待っていたら変わったかなって」
リリーは伝言アイテムを取り出して、ジョンに見せた。
差出人の名前は、この世界にはいない人物の名前。日付は49日前。
「それも人生だ、かわいそうなお嬢さん。
ホンモノは一度きり」
抒情詩を朗読するように、ジョンは言った。
「そうだね。
おじさんは明日から、どうするの?」
リリーは立ち上がった。
「ニセモノを楽しむとするよ。
この世界を愛しているんだ」
「幸せだね」
「そうとも、君と同じぐらいにはね」
「そっか。
サヨナラ」
「かわいそうなお嬢さん。
またね、というのが礼儀だよ」
ジョンが呼び止める。
「二度と会えなくても?」
「《イッグドラシル》には別れが似合わない」
ジョンは言った。
確かにそうかもしれない。仮想現実には明確な別れがない。
プレイヤーが今日ログインしていなくても、明日はログインしているかもしれないのだ。49日前のリリーがログインしていなかったように。
「じゃあね」
リリーは言い直す。
「終幕の先で待っているよ」
「ゴドーみたいに?」
「そう、ゴドーみたいに」
ジョンは笑った。
リリーには、そう見えた。
「じゃあ、またね」
百合ばかりをアイテムポーチに持っている少女は、世界から立ち去った。